
【ふわっと全科目を眺める眺める】「社労士試験 徴収法 有期事業の一括」過去問・徴-7…
このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペー…
過去問

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペー…

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペー…

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペー…

増加概算保険料は、その要件と延納について押さえておくようにしましょう。追加徴収の概算保険料は、納付の方法と納期限を理解しておき、延納についても認識をして…

今回は概算保険料の延納について見ていきたいと思います。延納は、継続事業と有期事業の違い、金額の要件や事務組合への委託などいろいろな要素が絡み合っています…

概算保険料の申告・納付は、一括有期事業を含んだ継続事業と、有期事業で扱いが違いますので、その違いを意識しながら知識を定着させましょう。過去問演習も大切で…

労働保険料の額には、どんな種類のものがあって、どのように計算されるのかは徴収法の根っことも言える項目ですね。社労士試験でも、色々な角度で出題されているの…

継続事業の一括は、有期事業の一括や請負事業の一括と違うところに意識しておくと知識の整理がしやすいです。たとえば、継続事業の一括は、他の一括と違って法律上…

今回は、徴収法の請負事業の一括について取り上げたいと思います。「一括」については、有期事業の一括や継続事業の一括もあったりして、知識がごちゃごちゃになる…

徴収法で「一括」はよく取り上げられる項目の一つですが、要件がきちんと整理されていないと知識が混同しやすく、定着しにくい可能性があります。なので、問題演習…

保険関係は、事業の廃止や暫定任意適用事業をやめるときに消滅しますが、社労士試験では、保険関係が消滅するタイミングや必要とされる手続きなど色々な角度で問わ…
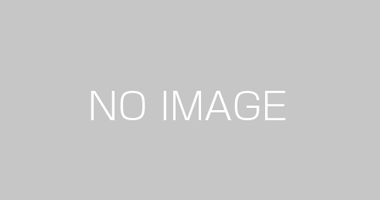
徴収法は、手続きの方法を規定した法律のためか、無味乾燥なイメージを持っているのは私だけでしょうか。苦笑「何を」「どこに」「いつまでに」「提出」みたいなも…

時効や書類の保存については、他の科目でも出てくる論点になっていますので、これを機に合わせて復習をしておくのもいいですね。たとえば、労基法での賃金の請求権…

今回は、労働保険料の負担と不服申立てについて取り扱った過去問を集めてみました。労働保険料は事業主と被保険者でどのように負担して納付するのか、その流れにつ…

私が受験勉強をしているとき(今でもそうですが)、労働保険事務組合と直接関わることがなかったので、労働保険事務組合のイメージがつかず、勉強していてもピンと…

今回は、継続事業のメリット制について見ていきたいと思いますが、何度見てもメリット制の苦手意識は完全には取れないです。苦笑でも、何度も触れることで…

今回は、徴収法から滞納に関する措置について出題された過去問を集めてみました。労働保険料を滞納すると、政府から督促がかかるのと、利子として延滞金がかかるこ…

今回は印紙保険料について出題された過去問を集めて見ました。印紙保険料は、ほかの概算保険料などと取り扱いが違うので、別ものとして捉える必要がありますが、…

徴収法での口座振替での納付については、まずは、口座振替による納付ができるものとできないものを区別することがスタートかと思います。なので、口座振替は銀行に…

確定保険料は、その名のとおり労働保険料が確定した旨の申告と納付を行うものです。この記事では、その確定保険料の申告と納付がどのような流れで行われるのかを取…

今回は、増加概算保険料と追加徴収について取り上げたいと思います。これらはどちらも、概算保険料の一部ですが、「どんな要件で成立して」、「本体の概算…

社労士試験の受験勉強をしていて、徴収法の「延納」は苦手イメージが正直ありました。継続事業と有期事業の違いを押さえることもそうですが、計算問題が出たらどう…

今回は、概算保険料・確定保険料の申告と納付について見ていきたいと思います。継続事業や有期事業、有期事業の一括といった事業ごとに要件を見ていくことで、きち…

労働保険料は徴収法の根っこと言えるかもしれませんね。保険料の定義をきっちりと押さえておかないと、この後の概算保険料や確定保険料、印紙保険料につなげること…

請負事業の一括については、有期事業の一括や継続事業の一括と並んで社労士試験でよく出題されています。注意しないといけないのは、それぞれの一括の要件とすり替…

今回は「継続事業の一括」について取り上げたいと思います。継続事業の一括が成立するための要件であったり、一括で出来ること出来ないことなどを取り扱った過去問…

「一括」は徴収法においていくつかある関門の一つと言っていいでしょう。一口に一括と言っても、有期事業、継続事業、請負事業のそれぞれに一括の要件があり、一括…

今回の徴収法では、徴収法の目的条文と、事業の基本となる一元適用事業や二元適用事業について取り扱った過去問を集めてみました。ややこしいのは、保険関係成立届…

徴収法での罰則は、事業主だけでなく労働保険事務組合も対象になることがあり、罰則を課す目的は労働保険料の納付にフォーカスしていますね。事業主や労働保険事務…

労働保険事務組合については、社労士試験でよく出題されていますが、事務組合についての問題は得意ですか?私は受験勉強をしているとき(今でもそうですが)事務組…