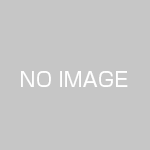今回は、時効について見ていきたいと思います。
時効の年数については労災保険法などと違ってシンプルでいいのですが、年金記録を訂正した時の時効の取り扱いなど注意する箇所がありますので一つ一つ見ていきましょう。
それでは、最初の問題に入っていきたいと思います。
まずは、厚生年金法で登場する時効の年数について確認していくことにしますね。
保険料を徴収する権利の時効

(平成23年問6A)
保険料を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき、時効により消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料などの徴収金の徴収や還付を受ける権利は、「これらを行使することができる時」から「2年」を経過すると時効により消滅します。
この徴収金の時効は2年ですが、次に出てくる保険給付については、別途定められていますので区別しておきましょう。
保険給付を受ける権利の時効は?

(平成23年問6C)
保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、時効により消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険給付を受ける権利は、徴収金の時と違い、「5年」を経過したときに時効により消滅します。
ちなみに、国民年金法では、年金給付の時効については5年となっていますが、死亡一時金の時効が2年になっているのでこの機に押さえておきましょう。
では、ここで具体的な保険給付名をあげた過去問で時効について確認をしておきましょう。
障害手当金の時効はどうなってる?

(平成29年問5A)
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
障害手当金の給付を受ける権利の時効は、2年ではなく「5年」です。
あと、労働基準法の退職手当の時効も5年でしたよね。
これを機に時効が5年のものをチェックしてみるといいですね。
さて、次は時効そのものの取り扱いについて見てみましょう。
次の問題では、年金が支給停止になったときに時効がどのようになるのか問われていますのでチェックしていきます。
年金が支給停止になったときの時効の取り扱い

(平成23年問6D)
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されたときは、更新する。
解説
解答:誤り
年金給付の「全額」が支給停止された場合、時効は更新されるのではなく、「進行しません」。
つまり、リセットされるのではなく、その場で時間がストップしているということですね。
では最後に、年金記録が訂正されてあらためて裁定された場合の時効について見ておきましょう。
年金の記録が訂正されているということは、5年の時効が過ぎてしまっていることもあり得ますから、
その際の時効の取り扱いがどうなるのか気になりますね。
年金の記録が訂正になった場合、時効になった保険給付はどうなるのか

(平成30年問3イ)
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者について、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法28条というのは、被保険者に関する原簿について定められていますが、訂正の請求についても規定されています。
で、年金の記録(原簿)が訂正されて保険給付を受ける権利について裁定(支給額などの決定)された場合は、
裁定の日までに時効が完成しているものについても、保険給付を受けることができるわけです。
年金記録の訂正の請求をしても時効だから受給できません、というのでは意味ありませんからね。
今回のポイント

- 保険料などの徴収金の徴収や還付を受ける権利は、「これらを行使することができる時」から「2年」を経過すると時効により消滅します。
- 保険給付を受ける権利の時効は、「5年」です。
- 年金給付の「全額」が支給停止された場合、時効は「進行しません」。
- 年金の記録(原簿)が訂正されて保険給付を受ける権利について裁定(支給額などの決定)された場合は、裁定の日までに時効が完成しているものについても、保険給付を受けることができるわけです。
毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

「思い出す」機会をどんどん増やしていきましょう。
昨日勉強したことは?1時間前の勉強内容は?1日でどんなことを学んだ?
「思い出す」行為、それはアウトプットですから、思い出す練習を積み重ねていきましょう♫
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!