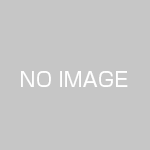このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から「児童手当法」について見てみたいと思います。
児童手当を受けるために必要な手続きや、支給額の改定時について確認していきましょう。
また、今日は社労士プチ勉強法についても書かせていただいていますので最後までお読みいただけましたら幸いです。
現況届はいつまでに提出する?

(平成25年問10イ)
児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
児童手当の現況届は、7月1日ではなく、「6月1日」から6月末日までの間に提出する必要があります。
ちなみに、私の住んでいる市によると、この現況届を期限内に提出しないと10月支給分の児童手当が支払われない可能性があるとのことです。
さて、子が産まれた場合など、児童手当の額に変動があった場合の取り扱いについて見てみましょう。
下の問題では、児童手当の額が改定されるタイミングがテーマになっています。
児童手当の額が改定されるのはいつ?

(令和2年問8C)
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童手当の増額改定は、認定の「請求」をした日の属する月の「翌月」から行われます。
増額改定は請求が必要なのですね。
逆に、減額改定の場合は、減額の「事由が生じた」日の属する月の翌月から改定が行われます。
今回のポイント

- 児童手当の現況届は、「6月1日」から6月末日までの間に提出する必要があります。
- 児童手当の増額改定は、認定の「請求」をした日の属する月の「翌月」から行われます。
社労士プチ勉強法
「勉強ツールにもリスク管理は必要です??」
先日、大手携帯電話会社で大規模な通信障害が起きましたね。
もし、勉強をする時にスマホやタブレットを使っていてデータ通信を利用している場合は影響を受けた人もいるかも知れません。
その時に、他に勉強をする術がないと非常に困ったことになりますね。
8月の本試験日まで少しの時間でも貴重ですので、勉強ツールを一つにまとめている場合は、リスク管理をしておいても良いかも知れませんね。
少し重たくなりますが、スマホと紙のテキスト、タブレットと暗記カードというように、カバンの中に複数の教材を入れておき、万が一に備えておくと安心でしょう。
ご参考になれば幸いです。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!