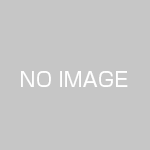このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金法における強制適用事業所と任意適用事業所について見てみたいと思います。
こちらの適用事業所の考え方は、厚生年金と同じですので、重複して勉強する手間が省けます。
適用事業所は、業種や人数、法人かどうかがポイントになってきますので見ていきましょう。
最初の過去問では、個人経営と法人の事業所の取り扱いがテーマになっています。
強制適用事業所となるのはどちらの方なのか見てみましょう。
個人経営と法人の違い

(平成23年問1C)
常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所となるかどうかは、業種が一つのポイントになっています。
適用事業所となる業種は、いわゆる法定16種と言われていますが、
範囲が広いので、非適用業種を見ておく方が早いです。
非適用業種となるのは、農林水産、理容・美容、接客娯楽、弁護士・社労士などの法務、宗教の事業などがあります。
問題文を見ると、飲食業は接客娯楽の事業になるので非適用業種となりますから、
個人経営の場合は、従業員が何名いても強制適用事業所とはなりません。
一方、法人の場合は、業種に関係なく、従業員が一人でも強制適用事業所となるのです。
では、法人の場合で、従業員が一人もいないケースはどうなるのでしょうか。
下の問題を見てみましょう。
一人社長の法人の場合は?

(令和元年問4ア)
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
解説
解答:誤り
先ほども述べたように、法人の場合は、業種や従業員の人数に関係なく強制適用事業所となります。
法人の代表者についても、法人から報酬を受けているのであれば、法人に使用される者となり、被保険者となります。
なので、問題文の場合でも適用事業所となるわけです。
さて、非適用業種が適用事業所となるには、任意適用事業所の認可を厚生労働大臣から受けることになります。
労災保険や雇用保険の場合、一定数の従業員が希望すれば、事業主は任意適用の申請をする必要があるのですが、
健康保険法ではどうなっているのでしょう。
もし従業員が被保険者になることを希望したら

(平成24年問8A)
従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。
解説
解答:誤り
健康保険法では、従業員が希望したとしても、事業主には任意適用の申請をする義務はありません。
逆に、事業主が任意適用の申請をする場合は、事業所に使用される者の2分の1以上の同意が必要となります。
さて、個人事業の強制適用事業所は常時使用する従業員の数が5人以上となっていますが、
もし、従業員が退職して5人未満になってしまった場合、任意適用事業所の申請が必要なのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
強制適用事業所の要件を満たさなくなった場合

(平成27年問5A)
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。
解説
解答:誤り
適用事業所が、その要件を満たさなくなった場合、任意適用の認可があったものとみなされるので、申請は必要ありません。
もし、申請を義務付けたとしても、事業主がその申請を忘れる可能性がありますし、
そのまま適用事業としておくほうが保険料の徴収ができますから、行政にとっても都合がいいですよね。
では、もし任意適用事業所の被保険者が、適用事業所から抜けて欲しい、という希望があった場合、事業主はどうすればいいのでしょうか。
最後に下の問題で確認しましょう。
被保険者が適用事業所でなくして欲しいと言ったら。。。

(令和2年問10C)
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。
解説
解答:誤り
被保険者から申出があったとしても、事業主は任意適用の取り消しの申請をする義務はありません。
ただ、事業主の方から、任意適用の取り消しの申請をする場合は、被保険者の4分の3以上の同意が必要となります。
今回のポイント

- 適用事業所となる業種は、いわゆる法定16種と言われていますが、非適用業種となるのは、農林水産、理容・美容、接客娯楽、弁護士・社労士などの法務、宗教の事業などがあります。
- 法人の場合は、業種や従業員の人数に関係なく強制適用事業所となります(法人の代表者も被保険者となります)。
- 健康保険法では、従業員が希望したとしても、事業主には任意適用の申請をする義務はありません。
- 適用事業所が、その要件を満たさなくなった場合、任意適用の認可があったものとみなされるので、申請は必要ありません。
- 被保険者から申出があったとしても、事業主は任意適用の取り消しの申請をする義務はありません。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!