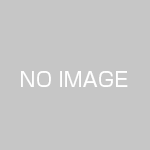健康保険組合の設立には、強制設立と任意設立があります。
強制設立は文字通り、厚生労働大臣が健康保険組合の設立を命じて設立されるもので、
任意設立の場合は、常時700人以上(共同設立の場合は3000人以上)の被保険者を使用している場合に設立できます。
(このとき、被保険者の2分の1以上の同意が必要です)
ただ、強制設立にしても任意設立にしても厚生労働大臣の認可が必要になります。
最初の問題は、この認可の権限が地方厚生局長に委任されているのかどうか、です。
では早速見ていくことにしましょう。
健康保険組合の設立の認可は地方厚生局長に委任されている?
(平成27年問7ウ)
健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
解説
解答:誤
健康保険組合の設立の認可や解散命令の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されていません。
やはり、設立の認可だったり、解散させたりするような重要な権限は、厚生労働大臣がガッチリ持っているんですね。
で、事業の運営をしていると事業計画や予算などを作成する必要が出てきますよね。
全国健康保険協会の場合は、事業年度開始前に事業計画と予算を作成して厚生労働大臣の認可を受ける必要がありましたが、健康保険組合の場合はどうなっているのでしょうか。
健康保険組合も厚生労働大臣の認可が必要??

(平成24年問4イ)
健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
解説
解答:誤
「厚生労働大臣の認可を受けなければならない」ではなく、「厚生労働大臣に届け出なければならない」です。
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければなりません。
全国健康保険協会との違いが出ていますね。
次は、健康保険組合の事業所を増やしたり減らしたりする時の手続きについての規定を確認しましょう。
ポイントは2つあります。
設立事業所を増減させるとき、誰の同意が要る?
(平成28年問1ア)
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意も得なければならない。
解説
解答:正
設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、
- 「事業主の全部」の同意
- 「その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上」の同意
が必要となります。
事業主の同意はわかりますが、被保険者の同意も必要なんですね。
やはり、被保険者も保険料を負担しているから、ということが関係しているんですかね?
さて、事業を運営していると、当然浮き沈みがあるわけで、健康保険組合とてそれは同じなのでしょう。
収支が均衡しない健康保険組合で、厚生労働大臣から指定を受けた健康保険組合を「指定健康保険組合」といいますが、財政を建て直すための計画を立てなければならないのですが、、、
財政の健全化計画に従わない健康保険組合はどうなる?
(平成30年問4A)
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。
解説
解答:誤
「当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併」ではなく、「当該健康保険組合の解散」を命ずることができます。
指定健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成して、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならないのですが、
その計画に従わない場合は、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができます。
ついに、健康保険組合が解散してしまった場合、残った被保険者はどうなるのでしょう。
誰かが引き継いでくれるのでしょうか?
健康保険組合が解散したら、誰が引き継ぐの?

(平成29年問1D)
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
解説
解答:正
問題文のとおりで、全国健康保険協会が、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継することになっています。
ちなみに、健康保険組合が解散するケースは次のとおりです。
- 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決
- 健康保険組合の事業の継続の不能
- 厚生労働大臣による解散の命令
となっています。
今回のポイント
- 健康保険組合の設立の認可や解散命令の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されていません。
- 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければなりません。
- 設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、「事業主の全部」の同意と「その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上」の同意が必要となります。
- 指定健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成して、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、その事業を行わなければならないのですが、その計画に従わない場合は、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができます。
- 全国健康保険協会が、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継することになっています。
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!