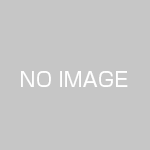今回は、遺族厚生年金の支給停止について見ていきたいと思いますが、
こちらの記事で取り上げているのは他の年金との絡みだったり、若年停止が主なものになりますので、一つ一つ見ていくことにしましょう。
最初の問題は、老齢厚生年金と遺族厚生年金の関係が論点になっています。
状況によっては両方の年金の受給権が発生する可能性は十分にありそうですが、どのように規定されているのでしょうか。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の関係とは

(平成29年問2B)
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができないことをまず押さえた上で、
どちらが優先されるのかというと老齢厚生年金の方です。
遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額に相当する金額が支給停止になります。
この受給権者については、65歳に達しているものに限られるので、
老齢厚生年金も特別支給ではなく本来の老齢厚生年金ということになりますね。
ちなみに、この受給権者が働いていて、老齢厚生年金の被保険者である場合、
在職老齢年金で支給停止に「ならなかった」金額の分の遺族厚生年金が支給停止になります。
では次は労働基準法との関係を見てみましょう。
亡くなられた原因が業務中の災害で、事業主から労働基準法に基づく遺族補償が行われる場合、遺族厚生年金がどのような形で支給停止が行われるのでしょうか。
労働基準法による遺族補償が行われるときは?

(令和元年問7E)
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働基準法第79条では、
「労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。」
と規定されています。
で、この規定による遺族補償が行われるときは、遺族厚生年金は、死亡の日から6年間その支給を停止されることになります。
さて、遺族厚生年金の遺族には、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、 子、父母、孫又は祖父母があげられますが、
次の問題では、配偶者と子についての関係が論点になっています。
遺族厚生年金の遺族の順位としては、配偶者と子は同順位となっており、
どちらが支給停止になるのかは、遺族基礎年金がカギになっていますので、問題文を読んでみましょう。
遺族厚生年金における配偶者と子の関係

(平成26年問1C)
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。(遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はありません)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、配偶者が遺族厚生年金の受給権がある間は、子に対する遺族厚生年金が支給停止になります。
しかし、配偶者が遺族厚生年金の受給権はあるのに、遺族基礎年金の受給権がなく、子に遺族基礎年金の受給権がある場合は、妻の遺族厚生年金が支給停止になります。
配偶者に遺族基礎年金が支給されるためには、子と生計を同じくしている必要がありますが、
子と生計が同じではないために、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生せず、
子に遺族基礎年金の受給権があるときは、配偶者の遺族厚生年金が支給停止になるというわけです。
さて、遺族厚生年金の支給要件には「若年停止」があります。
この内容がどういうものだったのか、次の問題で確認しましょう。
遺族厚生年金の若年停止の範囲

(平成24年問1C)
遺族厚生年金の受給権者が、死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫、父母又は祖父母であった場合、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給は停止される。(夫には遺族基礎年金の受給権はないものとします)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
夫、父母、祖父母に対する遺族厚生年金は、被保険者または被保険者であった者の死亡当時、55歳以上であれば受給権が発生しますが、60歳になるまで支給停止なります。
これを若年停止と言いますが、60歳までは仕事もしていて自分で稼げるだろうから遺族厚生年金を支給する必要はないよね、ということなんでしょうが、これは労災保険法にもありましたね。
ただ、夫については若年停止の要件が適用されないケースがあります。
先ほどの問題文にヒントがありますが笑、次の問題で確認しましょう。
夫が若年停止の対象外になる条件とは

(平成27年問5E)
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
妻の死亡当時、子と生計を同じくしていて夫に遺族基礎年金の受給権があるときには、夫に対する若年停止は、解除されます。
夫は引き続き子どもを育てていかなければなりませんから、遺族厚生年金を支給して生活を応援しようということですね。
今回のポイント

- 老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができないことをまず押さえた上で、どちらが優先されるのかというと老齢厚生年金の方で、遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額に相当する金額が支給停止になります。
- 労働基準法に基づく遺族補償が行われるときは、遺族厚生年金は、死亡の日から6年間その支給を停止されることになります。
- 原則として、配偶者が遺族厚生年金の受給権がある間は、子に対する遺族厚生年金が支給停止になりますが、配偶者が遺族厚生年金の受給権はあるのに、遺族基礎年金の受給権がなく、子に遺族基礎年金の受給権がある場合は、妻の遺族厚生年金が支給停止になります。
- 夫、父母、祖父母に対する遺族厚生年金は、被保険者または被保険者であった者の死亡当時、55歳以上であれば受給権が発生しますが、60歳になるまで支給停止なります。
- 妻の死亡当時、子と生計を同じくしていて夫に遺族基礎年金の受給権があるときには、夫に対する若年停止は、解除されます。
毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

試験に合格した時のご褒美はなんですか?
欲しかったものを買う?旅行に行く?何でも大丈夫です。
それを手に入れる瞬間をイメージしてみてください。
ファイトが湧きませんか?(^^)
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!