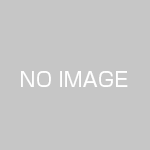時間外労働や休日労働で重要な論点といえば「36協定」がまず挙げられます。
社労士試験では、その36協定は、どうすれば効力が発生するのか、といったことも問われていますが、36協定以外の論点でも出題されていますので整理していくことにしましょう。
最初の問題は、災害などによる「臨時」の必要がある場合の時間外労働、休日労働について問題です。
「臨時」のときにはどういった手続きが必要なのかをチェックしましょう。
災害など理由で臨時に時間外労働、休日労働の必要があるときは?

(平成22年問4D)
労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ここでのポイントは、
- 「行政官庁の許可」を受けて、その「必要の限度において」行わせることができる(原則)
- 「事態急迫」のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、「事後に遅滞なく届出」
というところです。
ちなみに、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを命じることができます。
つまり、行政官庁が、「この仕事はそんなに緊急性ないでしょ」と判断すれば、働かせた分の時間分を休ませるように命令することができるんですね。
ちなみに、働かせた分の、時間外労働・休日労働や深夜労働についての割増賃金の支払はしなければいけませんので合わせて押さえておきましょう。
さて一般的に、労働者に時間外労働や休日労働をしてもらうためには、就業規則や労働契約書への明記、36協定が必要になるわけですが、そもそも労働者は時間外労働などをする義務があるのでしょうか。
判例から出題された過去問がありますので、それで確認してみましょう。
労働者は時間外労働などをする義務はない?

(平成27年問6ウ)
労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:誤
労働者は、
- 使用者が36協定を締結して
- 所轄労基署に届け出た場合、
- 就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、
- 労働契約を超えて労働する義務を負います。
なので、上記の要件を満たすのであれば、労働者は労働契約に定める時間外労働を超えて労働する義務を負うということになります。
先述したように、これは「日立製作所武蔵工場事件」の判例を基にした出題です。
気になる方は資料のリンクを貼っておきますので、ご自由に参考になさってくださいね。
参考資料:就業規則に関する主な裁判例(日立製作所武蔵工場事件 最高裁平成3年11月28日第一小法廷判決)
(リンクを開くと、他にも裁判例が記載されていますので、興味がある方はそちらもご覧になるといいと思います)
さて、先ほどの問題のように、労働者に時間外労働や休日労働をしてもらうためには、「36協定」が必要なわけですが、この36協定の効力はどのタイミングで発生するのか、という論点が次の問題です。
36協定は締結してしまえばオッケー?

(平成24年問5E)
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。
解説
解答:正
問題文の通りで、36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出ることではじめて効力が発生します。
なので、「36協定の締結」と「所轄労基署への届出」の2ステップを踏む必要があるということですね。
余談ですが、36協定の有効期間は1年にしているところが多くみられますが、うっかり更新するのを忘れてしまって、有効期間が切れた後に、時間外労働や休日労働をさせてしまうと違法になってしまいますので注意が必要です。
で、36協定を所轄労基署に届け出れば、時間外労働などができるようになるわけですが、坑内労働など、「健康上特に有害な業務」については、「法定労働時間+2時間」が限度です。
それをふまえたうえで、次の過去問をチェックしましょう。
坑内労働以外に、その他の仕事もした日の時間外労働はどうなる?

(平成29年問4B改正)
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問 において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、 1日について2 時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に 8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、本条(労基法36条)による協定の限度内であっても本条に抵触する。(問題文に一部補足しています。)
解説
解答:誤
問題文の場合、労基法36条には抵触しません。
「法定労働時間+2時間」が適用されるのは、坑内労働など健康上特に有害な業務のみの労働の場合です。
なので、問題文のように、健康に有害でない仕事もしていて「法定労働時間+2時間」になった場合には上記は適用されません。
もし、健康に有害でない仕事もしていたが、坑内労働だけの労働時間が「法定労働時間+2時間」を超えた場合は違法となります。
今回のポイント

- 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において行わせることができます。(原則)
- ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされています。
- 労働者は、
- 使用者が36協定を締結して
- 所轄労基署に届け出た場合、
- 就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、
- 労働契約を超えて労働する義務を負います。
- 36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出ることではじめて効力が発生します。
- 「法定労働時間+2時間」が適用されるのは、坑内労働など健康上特に有害な業務のみの労働の場合です。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!