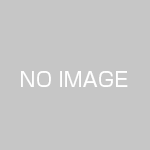今回は労働者の安全を守るために事業者にはたらきかける監督組織について取り上げた過去問を集めてみました。
この場合の監督組織というのは、都道府県労働局長や労働基準監督署長などのことを指します。
これらの監督組織がどのように事業者と関わっていくのか見てみましょう。
最初の問題は、労働災害を防止するための改善措置として、事業者に安全衛生改善計画の作成を指示するのは誰なのかが問われていますので確認していきますね。
安全衛生改善計画の作成を指示できるのはだれ?

(平成23年問9D)
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条の規定により、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(同法第78条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、安全衛生改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全衛生改善計画の作成を指示することができるのは、都道府県労働局長です。
この、安全衛生改善計画は、事業者だけで作成するのではなく、
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
ちなみに、重大な労働災害の再発を防止するために必要と認められる場合には、
特別安全衛生改善計画の作成を厚生労働大臣が指示することができます。
さて、そもそも労働者がケガをした場合にどのような処置が必要になるのか次の問題で確認しましょう。
労働者がケガをしたときの報告のルールは?

(平成25年問9D)
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
問題文の場合、死傷病報告書を所轄労基署長に提出する必要があるのは問題文のとおりですが、
休業の日数が4日に満たないので、1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月の各四半期ごとに、
死傷病報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出する形になります。
休業の日数が4日以上の時は、「遅滞なく」報告することになります。
では、起きた労働災害の原因調査を行政側が行う際、厚生労働大臣はある組織にその調査を行わせることができます。
それは一体どこなのか、次の問題で確認しましょう。
労働災害の調査をどこにさせることができる?

(平成25年問9C)
厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構に当該調査を行わせることができる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
通常、労働災害が起きたときに、原因を調査するのは、都道府県労働局や労働基準監督署に置かれている産業安全専門官や労働衛生専門官です。
しかし、労働災害の規模などの状況から判断して必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、独立行政法人労働者健康安全機構にその調査を行わせることができます。
さて、次は労働衛生指導医について見ておきましょう。
「労働衛生指導医」という名前は、安衛法の勉強をしているとチラホラ聞きますが、どのような役割を担っているのでしょうか。
労働衛生指導医の役割

(平成25年問9B)
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働衛生指導医は、都道府県労働局に置かれていますが、
都道府県労働局長が臨時の健康診断を事業者に指示するときに意見を聴くのが労働衛生指導医でしたね。
それ以外にも、今回の問題のように、作業環境測定や臨時の健康診断といった労働者の衛生に関する事務を行います。
で、都道府県労働局長が必要があると認めるときは、事業場の立ち入りや、関係者への質問、記録の検査を行うことができます。
ちなみに、労働衛生指導医は、任期が2年の非常勤の国家公務員で、厚生労働大臣が任命します。
では最後に、労働者がケガをした労働災害が起きていなくても、
たとえば火災などの事故が起きた時に行政に報告が必要になることがあります。
それはどのようなケースなのか確認しましょう。
事故が発生したときのルール

(平成25年問9E)
労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業場内で、ボイラーの破裂や火災、エレベーターのワイヤーロープの切断、クレーンの倒壊などの所定の事故が発生した時は、
所轄労基署長に報告書を提出する必要があります。
これは、事故が起きた時に、幸いにも負傷者がいなかっただけで、一歩間違えば労働災害につながる事故だったわけです。
労働災害を未然に防ぐために事故報告を出すことになっているんでしょうね。
今回のポイント

- 安全衛生改善計画の作成を指示することができるのは、都道府県労働局長です。
- 死傷病報告書は、休業の日数が4日以上の時は遅滞なく提出、4日未満の場合は四半期ごとに最後の月の翌月末までに所轄労基署長へ提出することになります。
- 労働災害の規模などの状況から判断して必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、独立行政法人労働者健康安全機構にその調査を行わせることができます。
- 労働衛生指導医は、都道府県労働局に置かれていて、作業環境測定や臨時の健康診断といった労働者の衛生に関する事務を行います。
- 労働災害が起きていなくても、事業場内で、ボイラーの破裂や火災、エレベーターのワイヤーロープの切断、クレーンの倒壊などの所定の事故が発生した時は、所轄労基署長に報告書を提出する必要があります。
毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

もし、今から2時間勉強できるとしたら、その2時間を30分ごとのエリアに分けましょう。
最初の30分は問題を40問解く、次の30分は〇〇をする、というように細切れにする方が集中力を発揮できますよ。
時間とやることを決めることが大切です♫
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!