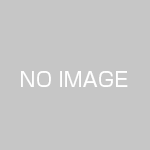労働契約といえば、雇用契約書や労働条件通知書などが思い浮かびますが、それらですべての労働条件をカバーできるかというと疑問ですね。
人数が増えてくると、就業規則のように、企業全体の基本的な労働条件を規定したものが必要になります。
今回は、労働契約法の中から就業規則について出題された過去問を集めました。
労働契約法で就業規則がどのような位置付けになっているのかを見ていきましょう。
最初の問題では、就業規則に書いてあっても、それが労働契約にならないケースもあるという論点になっているのですが、それはどんなものでしょうか。
就業規則に記載されていることでも労働契約にならないものがある?

(令和元年問3B)
就業規則に定められている事項であっても、例えば、就業規則の制定趣旨や根本精神を宣言した規定、労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては、労働契約法第7条本文によっても労働契約の内容とはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
就業規則というのは、労働者が業務をする上で守るべき規律や労働条件に関する具体的な項目について定めた規則のことですので、
基本的には、労働契約の内容は就業規則で定める労働条件になります。
ですが、就業規則の「制定趣旨」や「根本精神を宣言した規定」などは、立派なものだとは思いますが労働契約の内容とはなりません。
仮に労働契約であったとしても、モノサシが抽象的すぎてどう判断すればいいか分かりませんね。
さて、会社を経営していたら、残念ながら従業員の方を懲戒処分(戒めるために制裁を加えること)にしなければならないことも出てくるかもしれません。
しかし、使用者が従業員を懲戒するためには、事前にやっておかなければならないことがあります。
それは一体何なのでしょうか?
従業員を懲戒するならやっておかなければならないこと

(平成26年問1A)
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりで、使用者が労働者を懲戒するためには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を決めておくことが必要となります。
そもそも、使用者が持っている懲戒権は、企業の秩序を守り、円滑な運営を図るために、労働者の秩序違反行為に対して制裁を加えるものですが、
使用者が権利を濫用しないようにする必要もあります。
なので、使用者が懲戒をするためには就業規則で懲戒の種別と自由をあらかじめ規定しておいてルール化しなさい、ということになっているのです。
それでも、その懲戒が客観的に合理的な理由を欠いていて社会通念上相当として認められない場合は、その懲戒は権利濫用として無効になります。
このように、就業規則は、会社のルールとして重要な位置にあるわけですが、
労働者にきちんと周知していなければ、労働者の労働契約の内容は就業規則で定める労働条件とはなりません。
つまり、就業規則は労働条件にならない、ということになります。
では、就業規則を「きちんと周知」するというのはどういう状態のことを指すのでしょうか。
次の過去問で確認しましょう。
就業規則を周知するってどういうこと?

(平成27年問1E)
労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
就業規則の周知といえば、労働基準法にもありましたよね。
それは、
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
ですが、労働契約法の視点から見た「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも見ることができる環境にあればいいということですね。
さて、就業規則も、最初に作ってそのままずっと同じ形で運用されることは少ないかもしれません。
企業が長く経営されていると従業員の数が増えたり、色々な取り組みをしたりすることで就業規則は更新されていきます。
ただ、不幸なことに、企業の業績が思わしくなく、中には就業規則の内容が労働者にとっては不利益な内容に変更せざるを得ないことが起きるかもしれません。。
そんな場合、就業規則は労働者にとって不利益な労働条件に変更することはできるのでしょうか。
就業規則で決められている労働条件を不利益に変更することは可能?

(平成29年問1B)
「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであるが、就業規則に定められている労働条件に関する条項を労働者の不利益に変更する場合には、労働者と使用者との個別の合意によって変更することはできない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:誤
問題文の場合、就業規則の不利益変更について、労使の合意があれば変更できます。
基本的に、労働契約法では、労働契約の内容は、労働者と使用者が合意すれば変更できることになっています。
ただ、就業規則に関しては、使用者が一方的に決めるもの(労働者代表の意見は聴きますが)なので、基本的には就業規則を労働者の不利益に変更することはできません。
が、就業規則についても、労使の合意があれば変更できることになっています。
ただ、その合意に際して就業規則の変更が必要とされる場合はその限りではありません。
では最後に、就業規則の変更についてもう少し見ておきましょう。
次の問題では、就業規則の変更に含まれる範囲について問われていますので確認しましょう。
就業規則の変更に含まれるもの

(令和元年問3E)
労働契約法第10条の「就業規則の変更」には、就業規則の中に現に存在する条項を改廃することのほか、条項を新設することも含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
就業規則の変更とは、その内容に手を入れることだけを指すのではなく、新たに条項を追加することも含みます。
たとえば、労働者の教育訓練についての条項や、アルバイトの人を正社員に転換する規定などを追加すること指しますが、これらも就業規則の変更にあたります。
余談ですが、条項を追加したということで労基署に就業規則を提出する場合は、「変更届」になっていますね。
今回のポイント

- 就業規則の「制定趣旨」や「根本精神を宣言した規定」などは、労働契約の内容とはなりません。
- 使用者が労働者を懲戒するためには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を決めておくことが必要となります。
- 労働契約法の視点から見た「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも見ることができる環境にあればいいということになります。
- 就業規則に関しては、使用者が一方的に決めるもの(労働者代表の意見は聴きますが)なので、基本的には就業規則を労働者の不利益に変更することはできませんが、労使の合意があれば変更できることになっています。
- 就業規則の変更とは、その内容に手を入れることだけを指すのではなく、新たに条項を追加することも含みます。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!