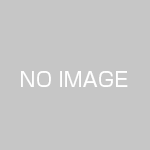社労士試験の受験勉強をしているとき、「障害厚生年金」と聞くだけで、
老齢厚生年金の在職老齢年金と並んで寒気のする項目で苦手でしたね。苦笑
社労士試験は、100点満点を取らなくていいので、すべての問題に正解する必要はないのですが、
足切りがあるため、苦手項目を切り捨てる勇気もなかったですね。
なので、どうしたかというと毎日5分でもいいので苦手項目に触れることにしました。
そして大事なことは、深追いせず基本事項をきっちり押さえることに徹しましたね。
ご参考になれば嬉しいです。
それでは最初の問題に入っていきましょう。
この問題は、ズバリ!「障害厚生年金の支給要件」が論点になっています。
問題文はごちゃごちゃしていますが、要件に当てはめて考えれば大丈夫なので読んでみましょう。
障害厚生年金の支給要件

(令和2年問4E)
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。
解説
解答:誤り
問題文の場合、障害厚生年金は支給されません。
障害厚生年金の支給要件は、
- 初診日において(厚生年金の)被保険者だったこと
- 障害認定日に障害等級(1〜3級)に該当していること
- 保険料納付要件を満たしていること
となっています。
問題文を見てみると、障害認定日の段階では厚生年金の被保険者のようですが、
「初診日」では国民年金の第1号被保険者だったので、
厚生年金の被保険者という要件から外れてしまうことになり、
障害厚生年金は支給されません。
ちなみに、障害認定日は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日のことを指しますが、
それまでに「治った」場合はその日が障害認定日となります。
それでは、この初診日についてもう少し見てみましょう。
次の問題では、「18歳」が論点になっています。
18歳でも障害厚生年金が支給されることはあるのでしょうか。
18歳が初診日でも障害厚生年金が?

(平成26年問3E)
厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害厚生年金の場合、初診日の段階で被保険者であればいいので、年齢は関係ありません。
高校を卒業してすぐに会社へ就職すれば被保険者になるわけですから、要件を満たせば障害厚生年金が支給されます。
国民年金の場合は、20歳にならないと第1号被保険者になれないので、そのあたりと引っかけてきたのかもしれませんね。
さて、先ほどは「18歳」がテーマでしたが、今度は「70歳以上」が論点になります。
70歳以上というと、高齢任意加入被保険者になるわけですが、障害厚生年金が支給されることはあるのでしょうか。
高齢任意加入被保険者でも障害厚生年金は支給されるのか

(令和2年問4B)
71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。
解説
解答:誤り
障害厚生年金の支給要件に「障害認定日」がありますが、年齢については規定がありませんので、
「初診日において被保険者」、「保険料納付要件」といった所定の要件を満たしていれば障害厚生年金は支給されます。
高齢任意加入被保険者は70歳以上なので、障害厚生年金??と思ってしまいますが、
冷静に支給要件を当てはめてみるといいですね。
では、次に事後重症について見てみましょう。
下の問題では、繰上げ支給の老齢厚生年金がからんできますので、障害厚生年金が支給されるのか確認しましょう。
障害厚生年金と繰上げ支給の老齢厚生年金

(令和元年問3B)
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりで、繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している場合は、事後重症の障害厚生年金は支給されません。
事後重症の障害厚生年金の場合、65歳に達する日の前日までに請求することになっています。
しかし、繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しているということは、
65歳以上に支給される本来の老齢厚生年金を繰り上げて受給していることになり、
年金的には65歳になったものとみなされます。
なので、年金的に65歳なったものとみなされている人について、65歳になるまでに適用される事後重症の障害厚生年金は支給されないということになるんですね。
では最後に、基準障害の障害厚生年金について見ておきましょう。
基準障害の障害厚生年金は、2つの障害を合わせたときに障害等級の1級か2級になれば、
それを併合した障害状態について障害厚生年金が支給されるものです。
この「基準障害」のもととなる「基準傷病」の位置付けについて次の問題で確認しましょう
基準傷病の位置付けとは

(平成29年問3エ)
厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
基準障害による障害基礎年金では、まず最初に、障害等級にならない程度の障害があり、その後、新たな傷病によって障害が出たときに、
最初の障害と後の障害を合わせたら1級か2級の障害等級の状態になれば、併合した状態の障害厚生年金が支給されるわけです。
で、基準傷病は後の傷病のことを指すのですが、初診日についても、他の傷病よりも後の日になっている必要があります。
また、65歳に達する日の前日までに併合して1級か2級の障害状態になっている必要があり、
請求については、65歳を過ぎてもできますが、支給は請求のあった翌月からになります。
今回のポイント

- 障害厚生年金の支給要件は、
- 初診日において(厚生年金の)被保険者だったこと
- 障害認定日に障害等級(1〜3級)に該当していること
- 保険料納付要件を満たしていること
となっています。
- 障害厚生年金では、初診日の段階で被保険者であればいいので、年齢は関係ありません。
- 障害厚生年金の支給要件に「障害認定日」がありますが、年齢については規定がありませんので、「初診日において被保険者」、「保険料納付要件」といった所定の要件を満たしていれば障害厚生年金は支給されます。
- 繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している場合は、事後重症の障害厚生年金は支給されません。
- 基準障害による障害基礎年金では、まず最初に、障害等級にならない程度の障害があり、その後、新たな傷病によって障害が出たときに、最初の障害と後の障害を合わせたら1級か2級の障害等級の状態になれば、併合した状態の障害厚生年金が支給されるわけですが、基準傷病は初診日について、他の傷病よりも後の日になっている必要があります。
毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

【効率の上がる勉強の進め方】
「10時から12時まで勉強」というように時間で計画するよりも、
「問題を10問解く」、「テキストを20ページ読む」
といった、量で設定した方が集中して取り組めます。
終わったら好きなことができる、というご褒美をつければ、スピードアップも可能です😊
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!