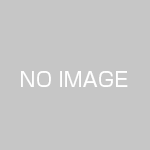社労士試験の勉強をする上で、労働基準法はすべての科目の基礎と言われていますが、その一つに、「労働者の定義」がなされていることにあります。
ケースによっては労働者に当てはまらないこともあります。
どこで線引きをすればいいのか、過去問を通じて見ていきましょう。
友達の引っ越しを手伝ったんですけど?
(平成29年問2ア)
何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。
解説
解答:正
この場合は、労働基準法は適用されません。
まあ、これは何となくイメージがつくような気がします。
引っ越しが長引いて、「8時間以上働いたから残業代よこせ」とか言ったら友人関係サヨナラですし、「お前を雇った覚えはねぇよ」って言われそうですし笑
それでは、労働基準法で、労働者とはどのように定義されているのでしょう。
法9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
ここでポイントなのが、
- 事業に使用される者
- 賃金を支払われるもの
です。
では、違う角度から見て見ましょう。
取締役であっても労働者??
(平成29年問2エ)
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。
解説
解答:正
たとえ、取締役という役職に就いていても、業務執行権や代表権がない、ってことは、誰かに指揮命令をうける「使用される者」になるので、「賃金を受ける」場合は、「労働者になる」ということですね。
今回のポイント
労働者とは、事業に使用される者で賃金を支払われる者、ということになります。
問題演習をこなしていくうちに、少しずつ感覚がつかめてくると思いますので、回数を重ねながら身につけていきましょう。