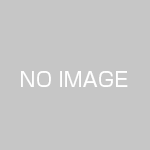労働保険料について、社労士試験では事業主と労働者の負担がどうなっているのか、などについてよく問われています。
また不服申立ては、法改正があってからもう数年経ちますので、だいぶ馴染んできたと思いますが、今回はそんな労働保険料や不服申立てについて出題された過去問を確認していくことにしましょう。
最初の問題は、雇用保険料の被保険者の負担分が論点になっています。
被保険者は雇用保険料をどこまで負担するの?

(平成22年雇用問8B)
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険の被保険者は、原則として、一般保険料の額のうち雇用保険率にかかる保険料の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1の額を負担することになっています。
つまり、
- 一般保険料のうち雇用保険料の額を出す
- 雇用保険料の額から二事業分を引く
- 残った額を半分にしたものが被保険者が負担する分になっています。
ちなみに、二事業分は事業主が負担します。
では、先ほどの問題には出てこなかった、一般保険料のうち労災保険料はどうなっているのでしょうか。
労災保険料も被保険者と事業主で負担するのでしょうか。
労災保険料も被保険者と事業主で負担するの?

(平成22年雇用問8C)
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。
解説
解答:誤
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、すべて事業主が負担するので、労働者が負担することはありません。
ただ、第一種特別加入保険料のように中小事業主が加入する分については、当然のことながら自分で保険料を払うことになりますね。
さて、次に日雇労働被保険者にかかる印紙保険料について見てみることにしましょう。
印紙保険料は一般保険料を負担することはない??

(平成22年雇用問8A)
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。
解説
解答:誤
日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担するだけでなく、先ほど述べた一般保険料の被保険者負担分も負担します。
ちなみに、事業主は、残りの一般保険料の事業主負担分と、印紙保険料の額の2分の1の額を負担することになります。
次は、不服申立てに入っていくことにしましょう。
冒頭に述べたように、不服申立てについては法改正があり、審査請求の流れが変わりました。
では、どのように変わったのかを確認しましょう。
審査請求は、労働者災害補償保険審査官に対して行う??

(平成28年労災問9イ)
概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。(問題文を再構成しています)
解説
解答:誤
概算保険料に係る認定決定についての審査請求は、「労働者災害補償保険審査官」ではなく、「厚生労働大臣」に対して行います。
これは、行政不服審査法の規定に基づいていて、厚生労働大臣に対して審査請求をするか、いきなり処分取消の訴えを提起することができます。
最後に、不服申立ての過去問を一問見てみましょう。
審査請求がダメなら再審査請求がある?

(平成25年労災問8E)
労働保険徴収法第19条第4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができ、その裁決に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
解説
解答:誤
「審査請求」は、厚生労働大臣に対して行うのは先ほど述べたとおりですが、「再審査請求」の規定はなくなり、審査請求の結果に不服なときは提起することになります。
今回のポイント

- 雇用保険の被保険者は、原則として、一般保険料の額のうち雇用保険率にかかる保険料の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1の額を負担することになっています。
- 一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、すべて事業主が負担するので、労働者が負担することはありません。
- 日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担するだけでなく、先ほど述べた一般保険料の被保険者負担分も負担します。
- 概算保険料に係る認定決定についての審査請求は、厚生労働大臣に対して行います。
- 再審査請求の規定はなくなり、審査請求の結果に不服なときは提起することになります。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!