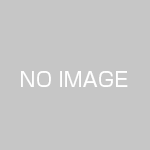労災保険法の通則には、保険給付を行うタイミングや、逆に給付を停止するタイミング、税金など、社労士試験では頻出の要件が並んでいます。
これは、他の科目にも当てはまりますので、ある程度の知識がついたら、横断的に整理してみるといいですね。
それでは、過去問をチェックしていきましょう。
仕事辞めても大丈夫ですよね?
(平成27年問6イ)
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
仕事中にケガをして働けなくなったからといって、保険給付が打ち切られたらたまったもんじゃないですよね笑。
それでは保険給付に税金はかかるのでしょうか。
まさか、労災保険に税金かかりませんよね、、、?
(平成27年問6ア)
労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ここで注意すべきなのは、問題文中の『金品」です。
規定でも、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない」とされています。
「金」は、年金や一時金といったお金のことを指します。
「品」は、療養の給付で受けた薬や包帯などの医薬品などの物品のことを言っています。
たとえば、国民年金法ですと、
「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。」
となっています。
このあたりは区別しておくといいですね。
次に、保険給付のタイミングについての過去問を見ておきましょう。
いつから保険給付してもらえるのですか?
(平成27年問7ア)
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
解説
解答:誤
「支給すべき事由が生じた月」ではなく、「支給すべき事由が生じた翌月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了します。」
“ 「翌月」で開始、その「月」で終了” と覚えておきましょう。
これは、年金の停止要件も同じです。
「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」
となっていますのでセットでおぼえられますね。
今回のポイント
- 労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません。
- 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできません。
- 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた翌月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了します。