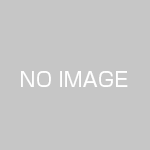このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働基準法から「労働契約の締結」について見ていきたいと思います。
労基法では、労働契約にある労働条件や、契約期間の長さについても規定がありますので、
どのようになっているのか見てみましょう。
労働基準法の基準に達していない労働契約の取り扱い

(平成25年問6A)
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働基準法は、強行法規ですので、労働契約で定めた労働条件のなかに、労基法に達しない条件があった場合、
その部分は無効となり、労基法の基準となります。
たとえば、「割増賃金は支払わない」と雇用契約書に書かれていたとしても、
その部分については無効になり、労基法の基準により時間外や深夜の割増賃金が発生することになります。
ちなみに、雇用契約書の全体が無効になるわけではなく、労基法の基準に達していない部分だけが無効になります。
さて、雇用契約の中には、契約期間は、「令和3年9月1日から同12月31日までとする」といった、有期労働契約があります。
この契約期間が次の問題のテーマになっていますので、どうなっているのか見てみましょう。
労働契約の継続雇用期間に上限はある?

(平成23年問2A)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
解説
解答:誤り
有期雇用契約は、契約期間の上限は、原則として3年になっていますが、契約を更新して継続期間が長くなることについては上限はありません。
ですので、問題文のように継続雇用期間が10年を超えてはダメという規定はありません。
ただ、契約期間が満了したからといって、無条件に雇止めができるか、といえばこれは別問題になります。
こちらについては、後でご紹介しますね。
で、先ほど、有期雇用契約の契約期間の上限は、原則として3年と書きましたが、
例外があり、満60歳以上の労働者や、高度の専門知識を持った者と有期の労働契約を結ぶ場合は、3年でなくても大丈夫です。
まず、満60歳以上の労働者との有期雇用契約について見てみましょう。
満60歳以上の労働者との労働契約の期間

(平成29年問3A)
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。
解説
解答:誤り
満60歳以上の労働者と期間の定めのある労働契約を結ぶ場合は、労働契約の期間は5年まで可能です。
なので、問題文のように65歳に達するまで、という規定にはなっていません。
たとえば、63歳の労働者と5年の労働契約を結ぶことも可能なわけですね。
では次に、高度の専門知識を持った者と有期の労働契約について確認しましょう。
高度の専門知識を持った者との有期労働契約の上限は?

(令和2年問5ア)
専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高度の専門知識を持った者との労働契約の期間も、満60歳以上の者と同じく、5年とすることができますが、
あくまでも高度の専門知識を使った業務をする場合に限られます。
たとえば、社労士の資格を持った人に、総務や人事の部門で社労士の知識を活かした業務をしてもらう場合ですね。
なので、社労士資格とは関係のない業務に就かせる場合は、原則どおり労働契約の上限は3年となります。
さて、先ほど雇止めのお話をしましたが、使用者が有期労働契約を結んだ労働者を雇止めをする場合、
所定の労働者については、一定のルールに則った上で雇止めをする必要がありますので、どういうことなのか見てみましょう。
雇止めをする場合のルール

(平成24年問2A)
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期労働契約を結んでいる労働者を契約期間の満了により雇止めをする場合、その労働者が、
「労働契約を3回以上更新しているか、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」
については、少なくとも契約の期間の満了する日の30日前までに、雇止めをする旨の通知をする必要があります。
30日前に通知をするという意味では、解雇の予告と同じようなイメージですね。
今回のポイント

- 労働基準法は、強行法規ですので、労働契約で定めた労働条件のなかに、労基法に達しない条件があった場合、その部分については無効となり、労基法の基準となります。
- 有期雇用契約は、契約期間の上限は、原則として3年になっていますが、契約を更新して継続期間が長くなることについては上限はありません。
- 満60歳以上の労働者と期間の定めのある労働契約を結ぶ場合は、労働契約の期間は5年まで可能です。
- 高度の専門知識を持った者との労働契約の期間も、満60歳以上の者と同じく、5年とすることができますが、あくまでも高度の専門知識を使った業務をする場合に限られます。
- 有期労働契約を結んでいる労働者を契約期間の満了により雇止めをする場合、その労働者が、「労働契約を3回以上更新しているか、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」については、少なくとも契約の期間の満了する日の30日前までに、雇止めをする旨の通知をする必要があります。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!